ニュース 鼻腔をくすぐるとはどういう意味ですか?. トピックに関する記事 – 「鼻孔をくすぐる」とはどういう意味ですか?
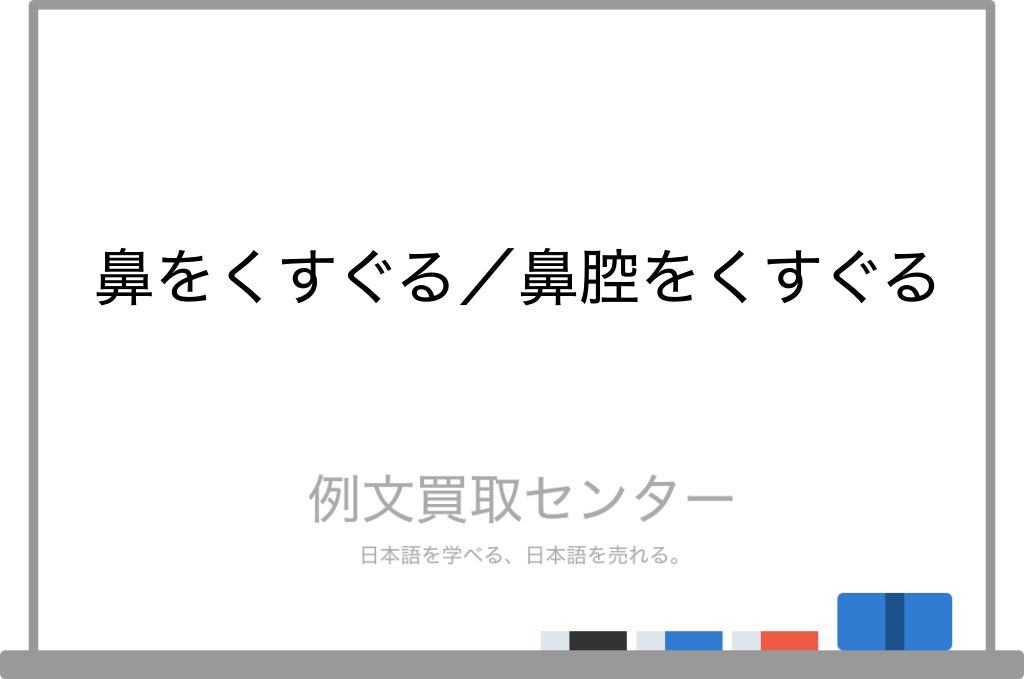
いい匂いがすることを「鼻孔をくすぐる」とした人が「鼻腔をくすぐる」を少し上回りました。「鼻腔」の例文・使い方・用例・文例
- 鼻炎,副鼻腔炎
- 鼻腔用潅注器の先端
- その犬は鼻腔内ワクチンを投与された。
- 急性副鼻腔炎は喘息の発作を引き起こすことがある。
- 鼻腔.
- 鼻腔(びこう).
- 鼻腔の検査(前鼻孔を通すか、鼻鏡を使って鼻咽頭を通すかのいずれか)
香りには2種類あり、食べ物を口の中に入れる前に鼻で感じる香りは「鼻先香」、食べ物を口の中に入れたあとに感じる香りは「口中香」と表現します。 多くの人たちは、香り成分が鼻先から嗅上皮に到達して感じる「鼻先香」だけを「香り」と言っています。
「鼻腔をかすめる」とはどういう意味ですか?思わずうっとりしてしまうほどのよい香り、鼻の中がとけてメロメロになってしまうような匂いを形容した表現。
鼻孔と鼻腔の違いは何ですか?
鼻の上部は骨により、下部は軟骨により支えられています。 鼻の内側の空間を鼻腔といい、鼻中隔によって左右2つの通り道に分かれています。 鼻中隔は骨と軟骨からなり、鼻孔(あな)から鼻の奥まで伸びています。手、羽根、筆などで体に触れ、むずむずとして笑いたくなるような感じを起こさせる。 精神や身体に、ここちよく感じられる刺激を与える。 おだてる。
副鼻腔と鼻腔の違いは何ですか?
鼻は「鼻腔」と「副鼻腔」という2種類の空洞からなります。 鼻腔は顔のほぼ正面、中央にあります。 副鼻腔は鼻腔を取り囲むようにあり、上顎洞(じょうがくどう)・篩骨洞(しこつどう)・前頭洞(ぜんとうどう)・蝶形骨洞(ちょうけういこつどう)から形成されます。

鼻の穴の中のことを「鼻腔(びくう)」といいますが、この鼻腔のまわりには、骨で囲まれた空洞部分が左右それぞれ4個ずつ、合計8個あり、鼻腔とつながっています。
鼻腔が臭う原因は何ですか?
鼻から嫌な匂いがする場合、鼻の奥にある副鼻腔のいう穴に膿がたまっていることが原因であることが少なくありません。 このような状態は、いわゆる、蓄膿症(ちくのうしょう)で、別名を慢性副鼻腔炎(まんせいふくびくうえん)と呼ばれます。 匂いは生ゴミのような生臭さが特徴で、強い不快感を感じます。においは鼻の奥の方にある、嗅粘膜という特殊な粘膜で感知します。 ここは通常の粘膜とは違う、嗅神経という神経の先が嗅繊毛という形になって直接「外」(鼻の中の空気の通り道)に飛び出しています。鼻の周囲の顔面の骨には副鼻腔と呼ばれる空洞があります。 副鼻腔には、頬の裏側にある上顎洞(じょうがくどう)、目の間にある篩骨洞(しこつどう)、 額の裏側にある前頭洞(ぜんとうどう)、鼻の奥にある蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)の4種類があります。

鼻づまりは、鼻内部の空気の通り道が狭くなることで起こります。 さまざまな原因があります。 左右の鼻の通り道の間にある鼻中隔という壁が曲がっている、鼻の粘膜がパンパンに腫れている、副鼻腔炎のせいで空気の通り道にポリープができているなどです。
「くすぐる」の使い方は?くすぐ・る【×擽る】
- 皮膚の敏感な部分を軽く刺激し、むずむずして笑いたくなるような感じを起こさせる。「 わきの下を—・る」
- 人の心を軽く刺激し、そわそわさせたり、いい気持ちにさせたりする。「
- 演芸・文章・会話などで、人をことさらに笑わせようとして、こっけいなことを言ったり、演じたりする。「
脇や首がくすぐったいのはなぜ?首とか脇の下とか、くすぐったい部位というのはおおむね人体の急所。 くすぐったいと感じる部分は、動脈が皮膚の近くを通っており、けがをすると多量の出血をともないかねない“危険部位”。 そのため付近には自律神経も集まって、外部からの刺激に対しては特に敏感になっている。
副鼻腔に溜まった膿はどうやって出せばいいですか?
病院では膿(うみ)を吸引したり、鼻の中に薬を吹きつける処置が行われます。 鼻の奥の副鼻腔まで届くように、抗生物質、抗炎症薬などの薬剤を、霧状にして口と鼻から吸入するネプライザー治療も一般的です。 また、内服する薬を処方することが多いです。

急性の副鼻腔炎の場合には1週間前後の抗生物質や炎症を抑えるお薬、又、局所療法としてうみを吸って鼻の中をきれいにする、更には、ネブライザー療法といって、抗生物質などの薬を細かい粒子にして副鼻腔まで届きやすくなるように蒸気を鼻から吸う療法などがあります。鼻は「鼻腔」と「副鼻腔」という2種類の空洞からなります。 鼻腔は顔のほぼ正面、中央にあります。 副鼻腔は鼻腔を取り囲むようにあり、上顎洞(じょうがくどう)・篩骨洞(しこつどう)・前頭洞(ぜんとうどう)・蝶形骨洞(ちょうけういこつどう)から形成されます。のどのうがいと併せて、鼻洗浄(鼻うがい)を行うことにより、アレルギーの原因となる物質がなるべく鼻腔内に付着しないようにすること、鼻水を流して鼻の通りをよくすることができます。 鼻の粘膜を湿らせておくことで乾燥を防ぎムズムズ感を軽減します。 また、風邪やインフルエンザの季節にも、細菌やウイルスが侵入することを防ぎます。
