ニュース 一瞬記憶が飛ぶストレスは?. トピックに関する記事 – ストレスで記憶が飛ぶのはなぜですか?
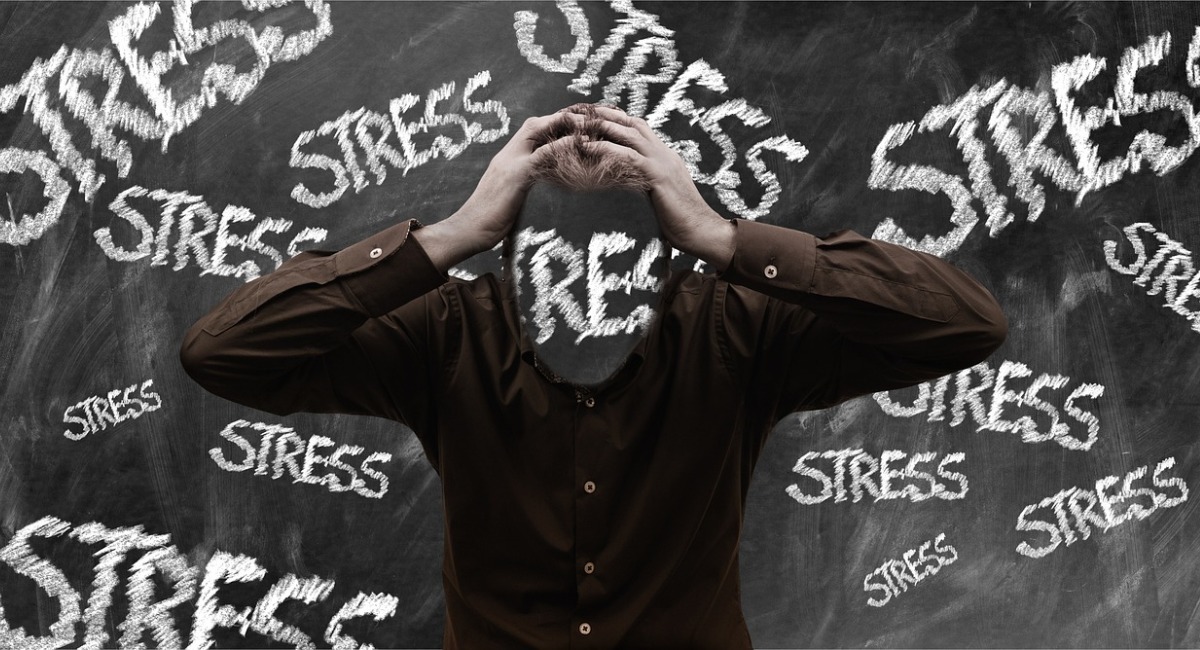
解離性健忘とは、心的外傷やストレスによって引き起こされる健忘(記憶障害)のことで、自分にとって重要な情報が思い出せなくなります。 記憶に空白期間がみられますが、その長さは数分から数十年にも及ぶ場合があります。 検査を行ってほかに考えられる原因を否定した後、症状に基づいて診断を確定します。概要 一過性全健忘とは頭の外傷を原因とせずに、一時的に新たな記憶ができなくなる状態をいう。 自分や家族の名前、職業、年齢などは覚えているが、今自分がどこにいて何をしているのかがわからなくなることが主な症状。 発症している間は、自分がしていることを記憶することもできない。つよいストレスを受けると脳内でコルチゾールというホルモンの分泌量が増加し(このホルモンはストレスホルモンとよばれます)、記憶にかかわる脳の「海馬」という部位に作用し、記憶力の低下につながるとされています。
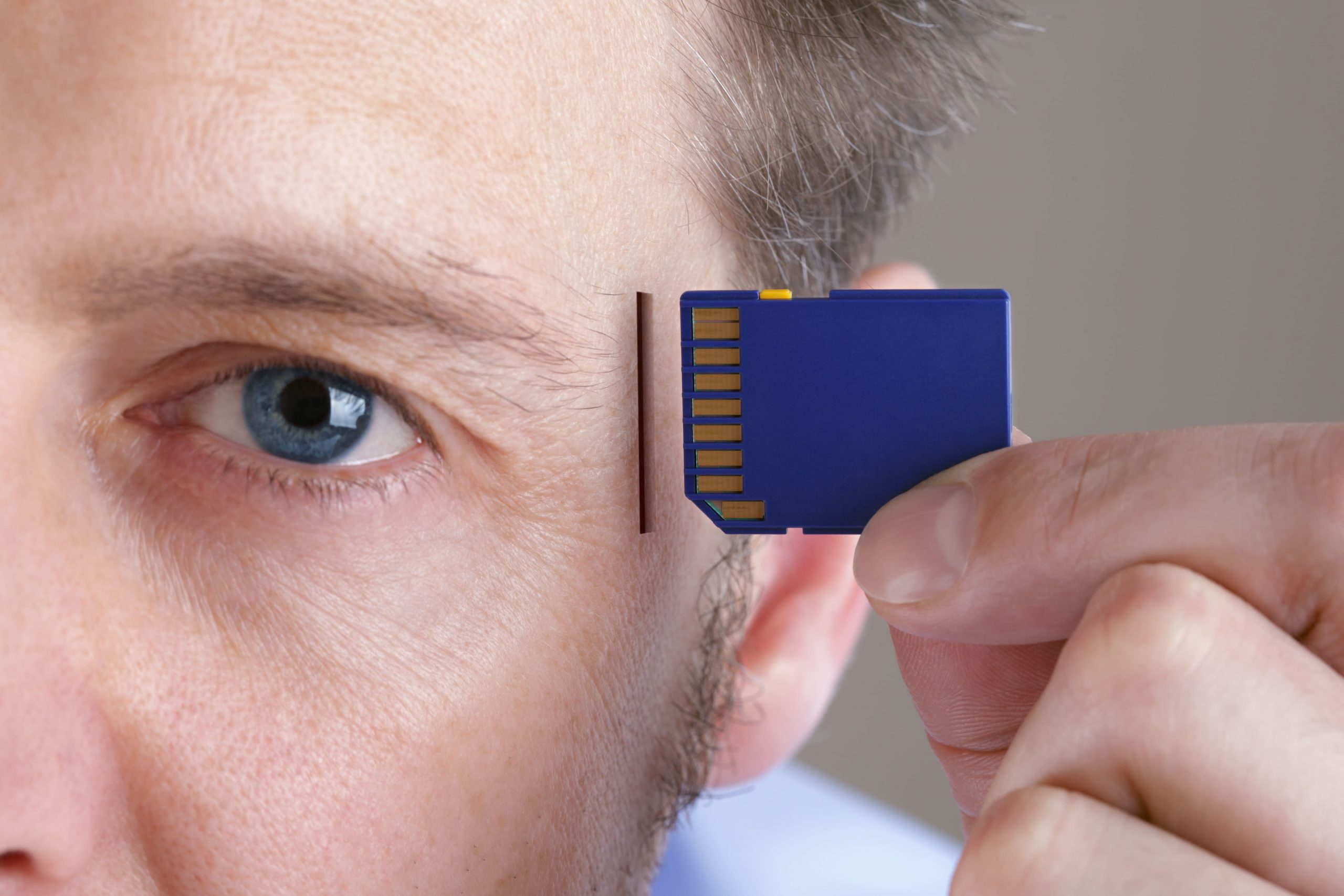
ストレスからくる物忘れの原因は?ストレスが多くなると、気を使ったり、悩んだり、考えたり… 時には眠れないほど常に脳を使い過ぎるようになり、脳が疲れると機能が低下しやすくなります。 さらに脳を活発に働かし続けることで脳の栄養も大量に消耗し、脳の栄養不足を引き起こします。 そのため、物忘れなど色々なトラブルを引き起こしやすくなるのです。
強いストレスで健忘になることがありますか?
解離性健忘は、通常、精神的なトラウマやストレスの影響を受けたときに発生することがあります。 例えば、強いストレスを感じた過去の出来事からの逃避や保護反応として起こることがあります。 突然の記憶の喪失が特徴的で、特定の期間や出来事に関する記憶が欠落します。人はストレスに対して自分を守るために様々な反応をします。 落ち込みが出たり、逆に退行(子供帰り)など様々です。 その中でストレスから一種「(自分を)隔てる」反応があり、これを「解離」と言います。 基本的には、これは「か強いストレスに圧倒された時に起こる反応」とされます。
ストレスによる健忘症とは?
ストレス(心因性健忘または解離性健忘)
このような心的外傷やストレスによって、引き起こされる健忘症を心因性健忘または解離性健忘ともいいます。 特徴的な症状は、特定の期間に関連する記憶が「思い出せない」または「部分的にしか残っていない」ということです。

すぐに病院を受診すべき、意識を一時失った場合に関連する病気もあります。
- 急性脳症
- 窒息
- 子癇
- 心室細動
- ウェスト症候群、点頭けいれん(West症候群)
- 房室ブロック・洞不全症候群
- てんかん
- 血管迷走神経反射性失神
脳を衰えさせる3大要因は?
脳の萎縮を進行させる要因として、加齢のほかに脳血管性疾患、飲酒、喫煙などが報告されています。ストレス(心因性健忘または解離性健忘)
このような心的外傷やストレスによって、引き起こされる健忘症を心因性健忘または解離性健忘ともいいます。 特徴的な症状は、特定の期間に関連する記憶が「思い出せない」または「部分的にしか残っていない」ということです。うつ病の物忘れは、記銘力(新たな事柄を覚えること)の低下です。 たとえば、新聞を読んでもなかなか頭に入らず、時間をかけて読んだのに内容を覚えていなかったり、仕事で打ち合わせをしたのに聞いたことが頭に入らず、結局覚えていなかったりします。 一方、認知症の場合は既知の事柄の記憶そのものが抜け落ちてしまいます。

解離性障害の治療 解離性障害の治療としては、薬物療法と心理療法が中心となります。 薬物療法では、解離症状を生じさせる起因となった心的外傷後ストレス障害などに対して、SSRIといった抗うつ薬を処方することがあります。 解離性障害に起因するあるいは付随する精神疾患への投与といったものが多くなります。
うつ病の症状に健忘はありますか?物忘れはうつ病でも起こることがある
上記で紹介したように、認知機能の低下による物忘れは、認知症だけではなくうつ病でも起こることがあります。 これは、ストレスなどによって一時的に脳機能が低下することが原因で引き起こされる物忘れで、年齢を問わずに起こり得る症状です。
めまいで一瞬意識が飛ぶ原因は何ですか?一瞬クラっとするめまい
血圧が下がり過ぎる原因には、睡眠不足や過労、二日酔い、感冒(いわゆる風邪)、脱水症、貧血、不整脈、糖尿病、自律神経失調症などがあり、不安やストレスが影響する場合もよくあります。 血圧が下がり過ぎる程度が強いと、意識を無くしてしまう場合(一過性意識消失)があります。
意識が飛ぶのは失神ですか?
脳全体の血液の流れが一時的に悪くなって、脱力を伴い、数分間(多くは5分以内)意識消失した状態のことを「失神」と言います。 意識回復までの時間が長い、目はすぐに覚めたがもとの状態とは違う状態にまる場合は、「失神」とはいいません。

昔の人は40歳を初老としていました。 最近はMRIなどの画像診断が進歩して脳の形態を詳しく見ることができるようになりましたが、それによりますと脳の萎縮は45歳ごろから始まり、60歳を過ぎるとかなり加速されることが分かってきました。 ですから50歳を過ぎれば、多少の脳の萎縮があったとしても異常とは言えません。本書でとり上げている脳に悪い7つの習慣は、①「興味がない」と物事を避けること、②「嫌だ」 「疲れた」とグチを言うこと、③言われたことをコツコツやること、④常に効率を考えること、⑤ やりたくないのに我慢して勉強すること、⑥スポーツや絵などの趣味がないこと、⑦めったに人を ほめないこと、である。落ち着かない、不安になる:常に何かが不安で、場合によっては居ても立ってもいられず、うろうろと動き回ったり、同じ行動を繰り返したり、何か気を紛らわせるような行動(飲食、飲酒、喫煙、運動、趣味など)を取るようになります。
