ニュース ラムネはなぜビー玉が入っているのか?. トピックに関する記事 – ラムネのビー玉は何のために入っていますか?

清涼飲料水Q&A 【サイダー・ラムネ】
ラムネ玉(ビー玉)が栓の役割をするためです。 中身に含まれている炭酸ガスの圧力で口ゴムとラムネ玉が圧着されて栓になっています。日本では大阪の徳永玉吉(徳永硝子の創業者)氏が日本で最初に完成させて、“ラムネ瓶”として量産を開始、全国的なラムネの普及に貢献しました。 ビー玉栓のビンを発明したハイラム・コッド氏(1838-1887、イギリス)。 この人がラムネの生みの親とも言えます。玉入りラムネ瓶が製造され始めたころ、瓶のフタとして使用できるほど歪みのない玉を、規格に合格した玉ということで「A玉」、フタとしては使用できない規格外の玉を「B玉」と呼んでいました。 たくさん余ったB玉は、当時ラムネを販売していた駄菓子屋などで子供たちに配られていたそうです。
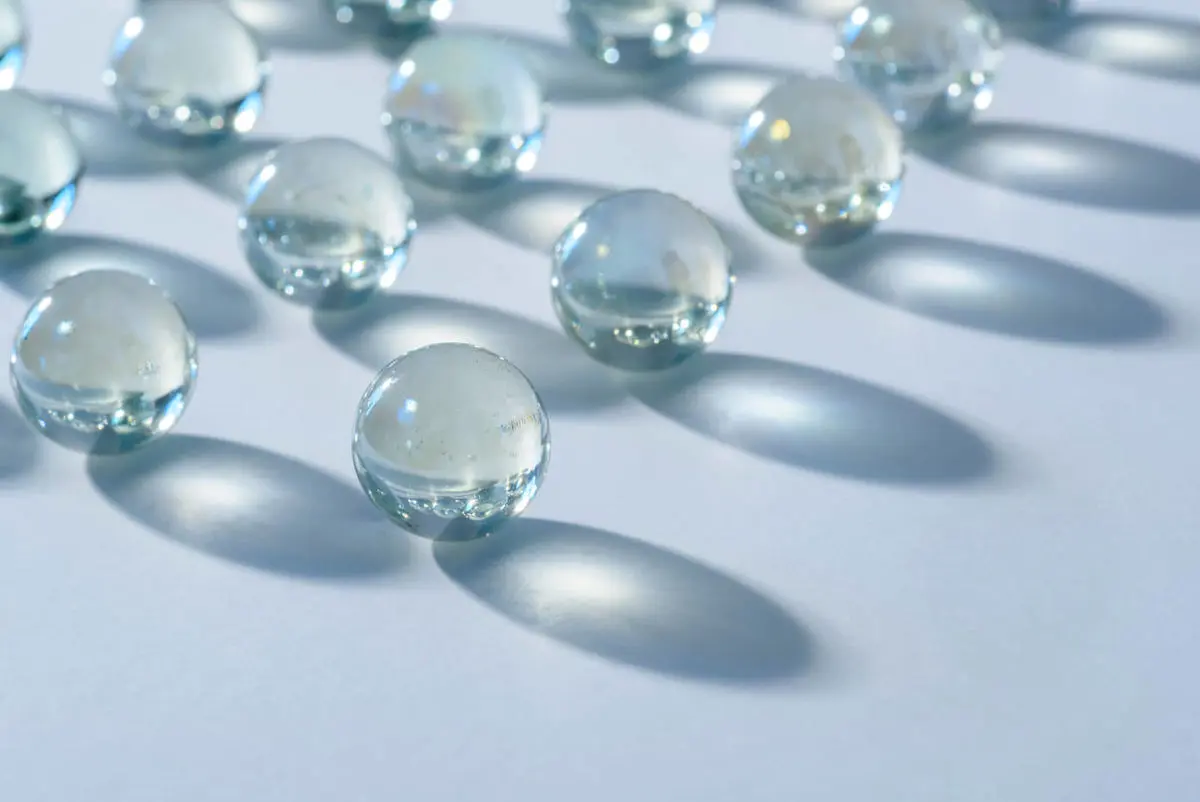
ビー玉が入った炭酸飲料は何ですか?現在ラムネとは、ビー玉で栓をした炭酸飲料のことをいいます。
ビー玉はA玉B玉ではない?
「ビー玉」 はガラスでできた玉の総称であり,ビー玉の中で,歪のないラムネの栓のガラス玉が「ビー玉 の A 玉」,ラムネの栓に使えない歪のあるガラス玉が「ビー玉の B 玉」である。ラムネの語源となったのは、英語の「レモネード(lemonade)」。 もとはフランス語の「limonade(レモン水)」から来ているとされます。 レモン果汁に砂糖を加えて水で割った飲み物で、家庭で簡単につくれることもあり、欧米ではとても身近な飲み物です。
ラムネの隠語は?
月賦のことをいふ。 ラムネは重曹を多量に含んで居る故に、飲むと頻りにゲツプ(月賦)が出るからいつたもの。 本来は多量に重曹を含む安物の飲料水であるが、之を飲むとゲツプーが出る所から月賦の隠語となつた、「素的な衣物ネーパトロンに買つて貰つたの」、「違ふわよラムネよ」などと女給達の話。

もともとは黒船来航とともに日本に伝わったもので、ラムネという名称は「レモネード」の聞き間違いから広まったとされる。 当初はコルク栓だったが、のちにイギリスで開発された専用瓶が伝わって主流になった。 似たものとしてサイダーがあるが、飲料自体が同じでも専用の瓶に入っていないものをラムネとは呼ばない。
ビー玉はなぜ逆さまに見えるのか?
虫メガネは近くのものは大きく見えますが、遠くのものは逆さまに見えますよね。 ビー玉も虫メガネと同じ1枚のレンズとして働いているので、逆さまに見えます。あの玉の名前は「エー玉」。 瓶のフタの役割をするガラス玉に、生産の過程で傷が入ったりすると中の炭酸が抜けてしまいます。 そこで、玉入りラムネ瓶が製造され始めた頃は、フタとして使える玉を「A玉」、使えないものを「B玉」と呼んでいたそうです。昔懐かしい、あの魅惑の玉は、実は大阪発祥らしい。 そもそも「ビー」の由来が以前から気になっていた。 詳しく調べてみた。 ビー玉遊びといえば、平安時代の「銭打(ぜにうち)」と呼ばれる賭博遊びがルーツとされる。

一般的にはビー玉と呼んでいますが、業界としては「ラムネ玉」と呼んでいます。 このビー玉の「ビー」は、ポルトガル語の「ビードロ」(ガラス)の略からという説と、ガラス玉の球状の規格「A玉」「B玉」から区別したという、2つの説があります。
ビー玉は誰が作ったのですか?舶来の玉は高級品のため、当初は木の実や粘土玉で代用されたが、1892(明治25)年、大阪市の徳永硝子(がらす)製造所が、ラムネ瓶の国産化に初めて成功。
ラムネ 一日何個まで?ここでは、森永のラムネを例にとり、食べ過ぎにならない食事量について見ていきましょう。 森永のラムネでは、一度に10粒、そして1日の合計で1本分が適量とされています。 なぜなら、同社のラムネ1粒は0.6gの糖質を含んでおり、10粒で6gとなるからです。
ラムネとサイダーは同じですか?
ビー玉入りの瓶の形をしているのがラムネ、それ以外はサイダーという違いです。 中味の違いはありません。

それゆえキリスト教では,ザクロは再生と不死に対する希望のシンボルとなった。 (2)((1)の実が熟すると口を開けるところから)ばか、あほうをいう隠語。 (1)拗音の漢字音「じゃく」の直音表記に由来する字音語。処女を云ふ。 処女のことをいう。 チンピラ語。1853年:ラムネは黒船と共にやってきた!
ラムネが日本に伝わったのは、1853年にペリー提督が黒船に乗り浦賀に来航したときです。 幕府の役人に積んでいた「炭酸入りレモネード」を艦上で振る舞ったことがはじまりといわれています。
