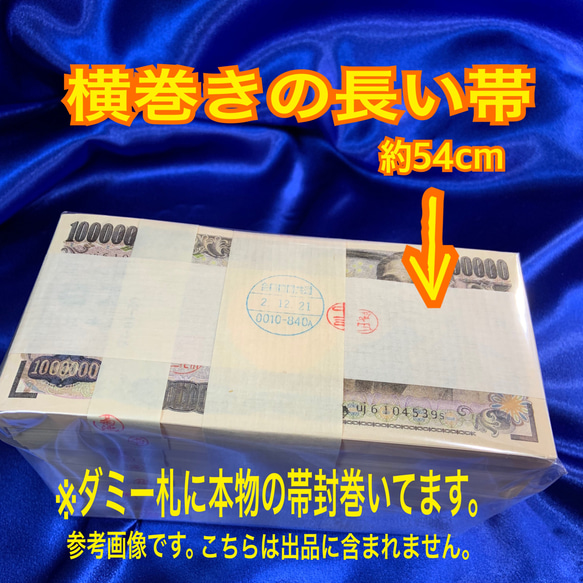ニュース お札に巻いてある紙は何ですか?. トピックに関する記事 – お札の薄紙は外してもいいですか?
お札に巻かれている薄紙は、神棚にお祀りする際には取り外していただき構いません。 この薄紙は「上巻紙」と呼ばれ、各家庭の神棚に祀るまでお札を清浄に保つための意味合いがあります。お札に巻いてある紙は剥がす
神宮大麻や氏神様などのお札には上巻紙という薄紙が巻かれていますが、これは神社から神棚までを清浄に保つことが目的です。 要するに「御札が汚れないためのカバー」なので、神棚にお祀りする際は薄紙をむいて中のお札だけをお祀りします。お神札「おふだ」には薄い紙が巻いてありますが、一見して和紙から文字が透けて見えるため神々しく感じられますが、これはお神札「おふだ」本体が皆様の手元に届くまで汚さないための「包み紙」なのだそうです。 「清浄を第一」とする新しいお神札は、この薄紙を取り外してからお祀りするのが一般的と伺いました。

神社のお札の白い紙は何ですか?「紙垂」は神聖であることを示す印で、悪いものを寄せ付けないためにつけます。 家庭では神棚やお正月飾りで紙垂を使いますし、大相撲の横綱土俵入りの際には、紙垂のついた注連縄を化粧まわしの上からつけるなど、神社以外の場所でも見かけることが多い身近なものですね。
お札の薄い紙はとるべきですか?
お神札を包装している薄紙は、家庭や会社までに汚れないようにするためのものです。 神棚や札立て(札差し)に納める直前に薄紙を取るとよろしいでしょう。 またお神札はサイズが様々です。お札を買うと、薄い和紙のような紙に巻かれている場合があります。 神棚にお祀りするときは、この紙は剥がすべきなのでしょうか? 結論から言うと「どちらでもかまわない」という意見が多いようです。
神棚のタブーとは?
神棚の「タブー」とは? 神棚のタブーは、神棚の掃除を怠ること、神棚に足を向けること、神棚に長期間お詣りしないこと、ずっと同じお神札や神棚を祀っていること、などがあります。 神棚は神様をお祀りする神聖な場所です。 日々ご加護くださる神様に失礼のないよう、タブーとなる行為を知っておきましょう。

水天宮の御神札と御守及び授与品(絵馬等)のみ神札所にてご返納が可能となります。 ※水天宮以外の御神札と御守、縁起物・正月飾り物はお受けになりました神社やお寺にお返しください。
神社にある白い紙の名前は?
神社や神棚のしめ縄についているヒラヒラした白い紙は「紙垂(しで)」といい、特殊な裁ち方をした紙のことです。 紙垂は自宅でも作ることができるので、ご自宅の神棚のしめ縄の紙垂をご自身で新調したり、万が一破れてしまったときに修復したりできます。“家内安全”や“無病息災”など、神社でもらったお札はどこへ置けばよい?
- 「神棚があれば、お札は内容に関係なく、全て神棚の中へお祭りください。
- 「神棚がない場合は、お札は家の中でできるだけ清浄な場所を選んで、目線より高い位置の、南向きもしくは東向きにお祭りしてください」
年に1度の御札交換のタイミングは、29日と31日を避けた12月中がおすすめです。 初穂料はかかってしまいますが、御札を返納して新しいものを拝受すれば、すっきりとした気持ちで新年を迎えられ、気も引き締まりますよ。 ぜひ年末の御札交換の際には、今回ご紹介した内容を参考にしてみてくださいね。

お神札(おふだ)について
お神札に巻いてある薄紙は上巻紙といい、お神札を各家庭の神棚へおまつりするまで清浄に保ち、汚れることのないように施されたものです。 神棚にまつる際には、取り外してからおまつりします。 お神札は一年に一度お取替えします。
伊勢神宮の御札は薄い紙で巻くのはなぜですか?伊勢神宮内宮の「角祓」。 うっすらと入った神紋が美しい薄紙。 もともと、持ち帰る間に汚れないようにという包装紙としての役割が強かった外紙ですが、お札を直接触るのは忍びない、御神名や神社名がそのまま見えるのは恐れ多いという方も多く、巻いたままお祀りしている場合も多いそうです。
神棚を置いてはいけない場所は?また、神棚を置くのにふさわしくない場所としては、トイレの近くやキッチンや洗面所などの水回り、人の出入りがあまりない部屋やドア・窓の上、床などです。 人の出入りがあまりない部屋だと暗くて光が少なかったり、トイレや水回りの近くだと神棚が汚れてしまう可能性があります。
玄関に神棚を置いてもよいですか?
日常的に人が上を通る場所や、見下ろせる場所におまつりすることはタブーです。 玄関やドアの上など人が頻繁に出入りする場所、トイレの近くなども適しません。
初穂料とは、お宮参りに際して神社に納める祈祷料のことです。 初穂料は8,000円で、4,000円追加すると安産祈願のお守りがもらえます。 また水天宮で初穂料を納める場合、のし袋は必要ありません。水天宮の初穂料は8,000円です。
初穂料は正式には紅白の蝶結びの「のし袋」に入れて納めますが、水天宮では包まずそのまま納めていただいて大丈夫です。 受付を済ませた後は、授与品と名前札を受け取り、御祈祷の時間まで待合室にて順番を待ちます。御幣とは 御幣とは、神様への捧げ物、お供え物を表し「幣」は貴重な品を意味しますが、神社によっては神様そのものを表し、御幣自体がご神体になったり、祭祀の際に依代となる場合もあります。 神棚や神社の奥に祀られている、2本の紙垂を竹や木で挟んだものが一般的なかたちです。