ニュース 「鹿の子」の古語は?. トピックに関する記事 – 鹿の子とはどういう意味ですか?

この『鹿の子』の意味は、編地の模様に由来しているそうです。 鹿の子編みした編み目が、子鹿の背中には白い斑点があります。 そのまだら模様に似ていることから『鹿の子』と言われるようになったそうです。かのこ‐まだら【鹿の子▽斑】
鹿の毛並みにみられる白い斑点。 ある地色に、白い斑点のある模様。か‐こ【鹿子】 《「かご」とも》シカ。 また、シカの子。
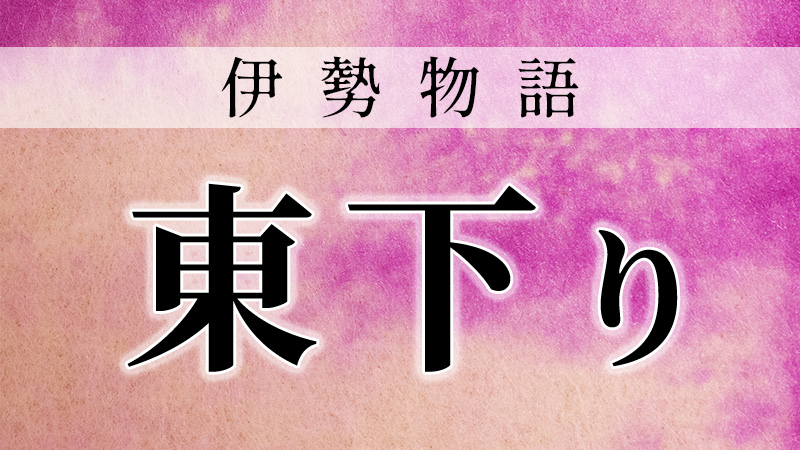
古文で「鹿の子まだら」とは何ですか?かのこ-まだら 【鹿の子斑】
鹿(しか)の体のように茶色の地に白い斑点(はんてん)のあること。
鹿の子の名前の由来は?
この『鹿の子』の意味は、編地の模様に由来しているそうです。 鹿の子編みした編み目が、子鹿の背中には白い斑点があります。 そのまだら模様に似ていることから『鹿の子』と言われるようになったそうです。鹿の子(かのこ) 三夏
はじめは雄も角がなく二年目から生えてくる。 公 園などで飼われている鹿は人懐こく、見開いた大きな目は特に可愛らしい。 『花火草』(寛永13年、1636年)に所出。 鹿は秋に交尾し、翌年の四月から六月にかけて出産する。
鹿の子絞りの由来は?
「鹿の子」という名前の由来は、できあがった模様が子鹿の斑点に似ていることから名付けられたと言われています。 「京鹿の子絞」(きょうかのこしぼり)は、京都で室町時代から江戸時代初期にかけて、辻が花染として盛んに行われるようになり、江戸時代中期に全盛期を迎えました。

鹿の子とは求肥を小さく纏めて餡で包んでから、蜜に浸けた豆をまぶしたお菓子で、鹿の子絞りに似ているのが名前の由来です。
古文で「鹿子」と書いてあったが読み方は?
か-の-こ 【鹿の子】
鹿。 「鹿(か)の子斑(まだら)」の略。 「鹿(か)の子絞(しぼ)り」の略。「慈姑」は「くわい」と読みます。 それなら知ってる!という方や、おせち料理で食べた、という方もいらっしゃるかもしれませんね。 くわいは、実から立派な芽が伸びるその形から、「食べると芽が出る」縁起のよい食べ物とされています。むら-むら 【斑斑・叢叢】
まばらに。 まだらに。
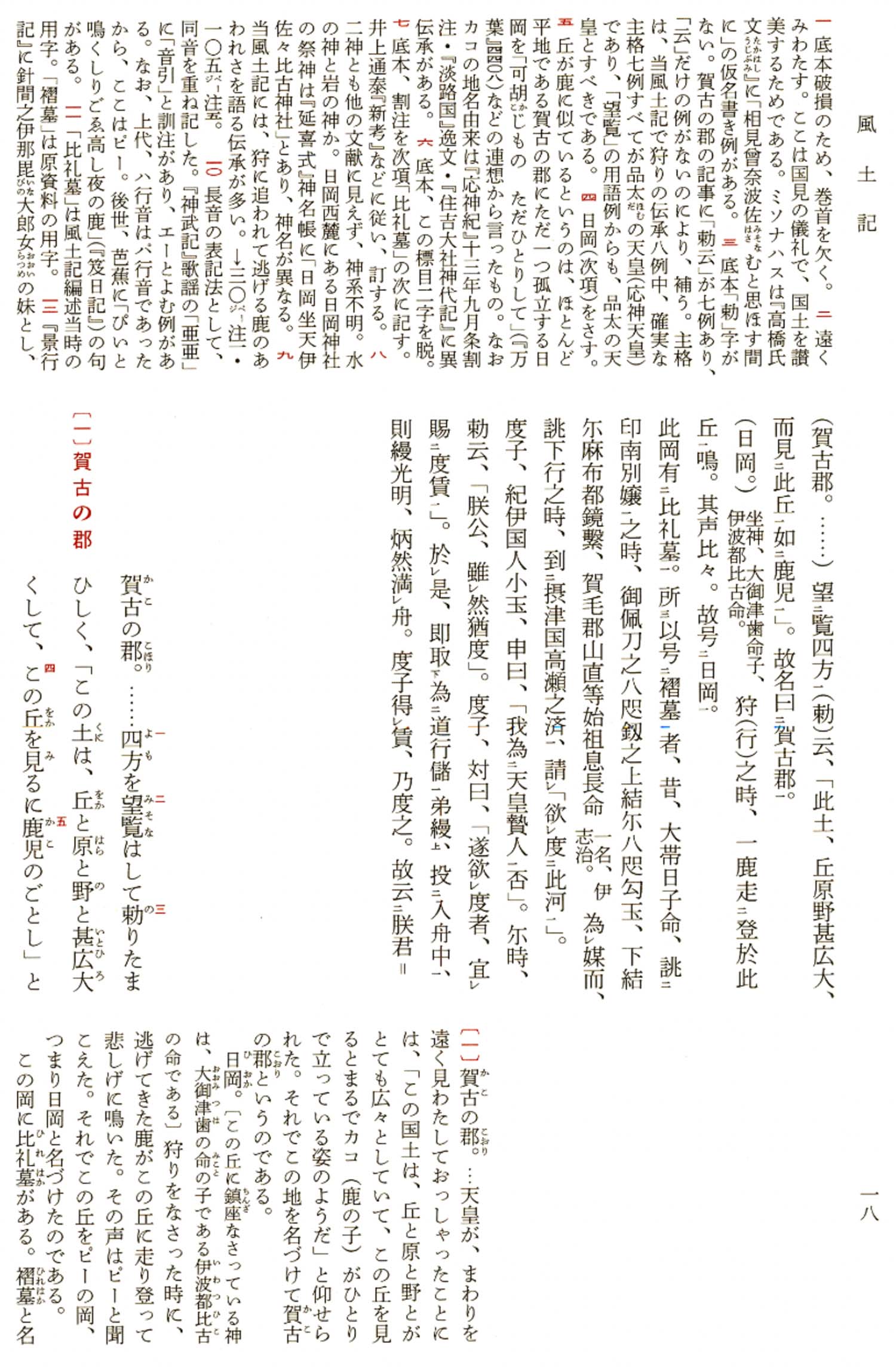
あざ・る 【戯る・狂る】
取り乱して動き回る。 [訳] 取り乱し動き回って私は請い祈ったが。 ふざける。
鯨の鹿の子の由来は?たっぷり含んだくじらの 脂肪分が、風味のある甘みを引き出します。 部位の説明 あご骨の周りにあたる部分で、筋肉に脂肪 が粒状に存在し、その模様が子鹿に似て いる事から鹿の子と呼ばれている高級赤 肉部位です。
鹿の子は夏の季語ですか?鹿は夏に産まれる。
朧月は春の季語ですか?
移動性高気圧が通過するのは春と秋ですので、おぼろ雲越しの月も春や秋によく見られます。 しかし、「朧月」という言葉は春の季語です。 秋の場合は「朧月」とはいわないのです。
鹿の斑点のように、丸く小さな白い輪が集まって模様を作り出す、京都発祥の技法を「京鹿の子絞り」といいます。 別名「疋田絞り」とも呼ばれるこの染め物は、模様の細かさから、完成までに一年以上かかることも珍しくありません。絞り染めは、日本では千数百年も前から行われており、宮廷衣装の紋様表現として用いられてきました。 括(くく)りの模様が子鹿の斑点に似ているところから「鹿の子絞り」と言われます。 室町時代から江戸時代初期にかけて、辻が花染として盛んに行われるようになり、江戸時代中期には、鹿の子絞りの全盛期を迎えました。愛知県常滑市にある老舗和菓子店で今人気なのが、なんと便器の形をした最中。 皮はもち米のみで作られ、便器の形になっています。 便座をあげて、中に北海道産の小豆で作った「粒あん」をたっぷりと入れていただくと…。 その名も『トイレの最中(さいちゅう)』324円。

