ニュース 「山崎」とはどういう意味ですか?. トピックに関する記事 – 山崎の先祖は?
越前国の一族。 赤松氏の一族で、『山崎家譜』によれば、赤松則村の子赤松氏範の子孫の肥前守某が山城国山崎村に定住し村名をもって姓にしたと伝える。 その七世の孫、長時に至って越前に下り朝倉孝景に仕えた。山崎とは元来、山が岬のように突き出た部分、あるいは半島を表す言葉であり、同様の地形をもつ場所の地名として多く使われている。 青森県弘前市山崎や神奈川県鎌倉市山崎、静岡県静岡市葵区山崎など山崎の付く地名は多い。山﨑家は、江戸時代中期、掛川藩旧伊達方村寺ヶ谷の旧家から分家し、万右衛門(才兵衛)が始まりとされます。
山崎という地名の由来は?地名の由来は定かでないが、大同年間(806年〜810年)に水野源内が移住し開拓したのを草分けとし、船見山の崎にある村であることから山崎と称したと伝えられている。 文和2年(1353年)の古文書に山崎村の地名が残っており、また吉祥院は養老7年(723年)に創建されたと伝わっている。
山崎家の家紋は?
山崎扇紋は、10橋の薄板で作られた『檜扇』に『平四つ目』を描く。 備中成羽藩山崎氏の定紋ということで山崎扇と呼ばれる。実は「やまざき」と「やまさき」、呼び方の差は出身地域の違いによるものです。 ハローページで「やまざき」と「やまさき」、どちらの呼び方が多いかを調べてみたところ、東日本では、濁点のつく「やまざき」さんが約97%。
山崎の別名は?
また平安前期、嵯峨天皇はしばしば山崎に遊び、漢詩を賦して山崎を 河陽 かや と称したので、河陽は山崎の別名として用いられた。

専門家によると、東日本では濁音が多く、西日本では清音が多くなるという不思議な法則があるそうだ。 たとえば「山崎」。 皆さんはどう読むだろうか? 実は、「やまざき」と濁って発音するのが東日本に多く、「やまさき」と濁らずに発音するのが西日本に多いらしい。
山﨑 何県?
山崎という場所は京都府の南西端に位置し、大阪府の北東にあります。 大阪府と京都府に隣接した場所であり、町名で言えば、京都府乙訓大山崎町と大阪府島本町の両町付近を広範囲でさす場所です。 ちょうど大阪と京都の県境があるので、観光資料で東西それぞれ別々のような感じがしますが、歴史的には同じ地域に属しています。まず大前提として、楷書としては﨑も崎もどちらも等しく正しいし、古代中国からどちらの字もあるので、どっちが新字・旧字とか略字とかではありません。 あと、漢和辞典では「﨑」(立)を俗字としているものもあるみたいなのだけど、俗字ではありません。 正式な異体字です。JIS第1水準および第2水準の文字のみ収録している為、「﨑」や「髙」などの外字は入っていません。
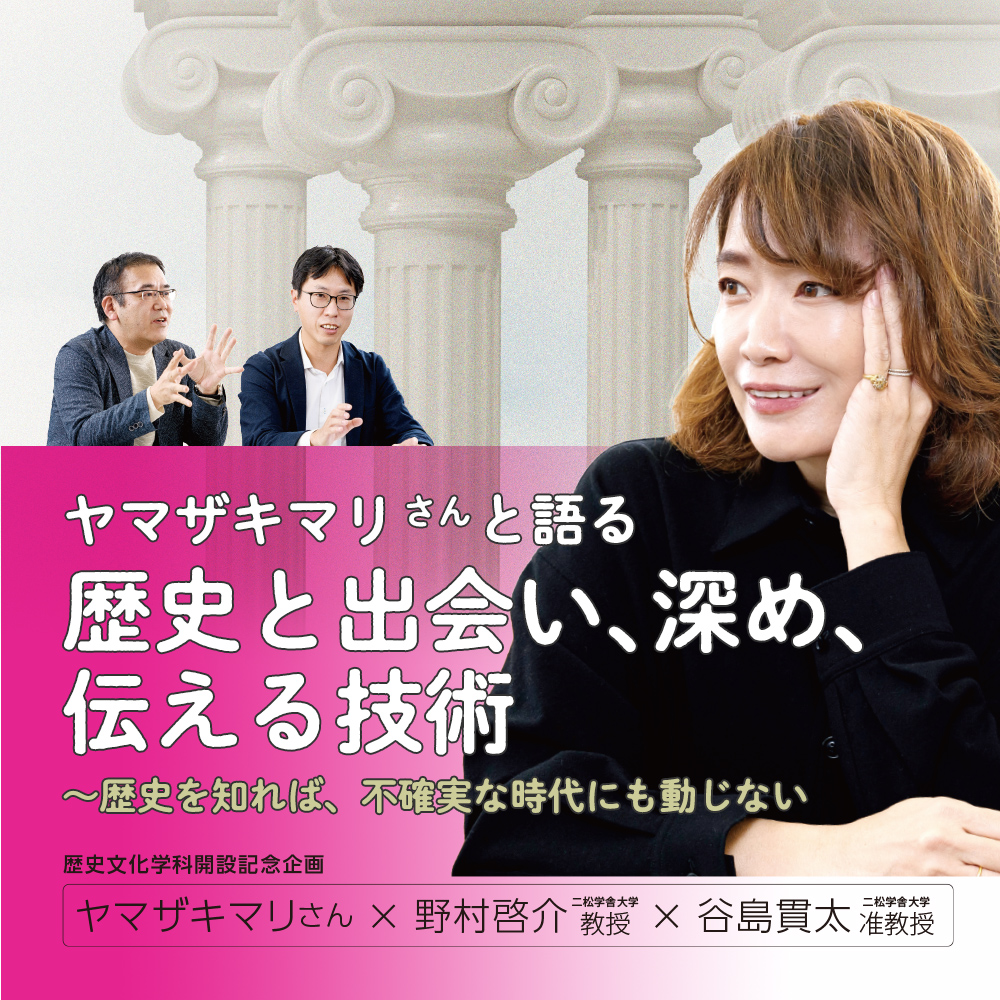
日本語には「連濁(れんだく)」という読み方のルールがあります。 「青空」や「本棚」のように、2つの単語が連結する時には、“2つ目の単語の最初の音が濁る”という決まりです。 この連濁のルールに従えば、「山崎」さんの読みは全て「やまざき」さんとなるはず。 なぜ、2通りの呼び方が存在しているのでしょうか。
崎と﨑のどっちが正しいですか?確認ができない場合、現在の常用漢字では「崎」を採用しているので、「崎」(大の方)を使っておけば失礼はないでしょう。 PCによっては「﨑」(立の方)がない場合もありますしね。 でも実際はどちらでも大丈夫。
山崎と山﨑、どちらの呼び方が多いですか?実は「やまざき」と「やまさき」、呼び方の差は出身地域の違いによるものです。 ハローページで「やまざき」と「やまさき」、どちらの呼び方が多いかを調べてみたところ、東日本では、濁点のつく「やまざき」さんが約97%。
